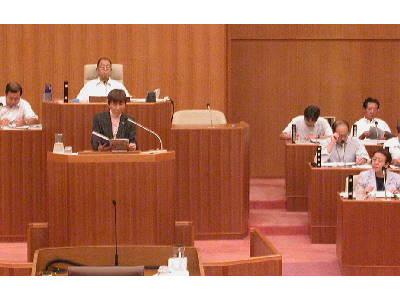| |
平成22年6月、宝塚市議会本会議が開催されました。
私の質疑および当局の答弁をご報告します。(抜粋)
| 1. | 子宮頸がん予防について | |||||
| 子宮頸がんは、20才代の女性では、乳がんを抜いて発症率が一番高いがんで、年間1万5千人以上が 発症し、約3500人が 亡くなっている。 しかし近年、子宮頸がんの原因はヒトパピローマ ウィルス(HPV)の感染であることが明らかになり 予防ワクチンが開発され、唯一ワクチンで予防できる がんとなった。 |
||||||
| (1) | 子宮頸がん検診の受診率を、先進各国と比べると、欧米では80%と高いのに、日本は20%程度にとどまっている。 本市での子宮頸がんの検診率を引き上げる 取り組みは。 | |||||
| ■市長 | 無料クーポン券を配布し、受診率向上に向け啓発活動を継続していく。 | |||||
| (2) | 本市における子宮頸がん予防ワクチン接種を 促進するための啓発や相談体制、さらに接種後のフォローアップ体制の構築について。 | |||||
| ■市長 | 市民が安心してワクチン接種を受けられるよう、副反応に関する情報収集を行い、ワクチンの安全性と有効性に関する見解を、医師、専門機関等に確認していく。 | |||||
| (3) | 子宮頸がん予防ワクチン接種の無料化をすでに実施している自治体があることが報道されている。 兵庫県内三木市においては、先日 中学1年生に説明プリントが配布され、「子宮頸がん検診と予防ワクチン」という演題での市民公開講座も 開催されるとのことである。インターネットで 無料券をダウンロードできるようにもなっているし、問い合わせ・申請窓口も2カ所設けられている。 このように同じ兵庫県内においても積極的に行政が動きだしたところがあるのが現状である。 住んでいる地域によって、また経済的状況によって「生命の格差」が生じることがあってはならない。 加えて、このワクチン接種によって、将来、我が国における子宮頸がんの発生を約70%減少させることが期待できる・・とされ、子宮頸がんに要する医療費を大幅に抑制することにつながる。 本市においても、子宮頸がん予防ワクチンの公費助成による負担軽減を図るべきではないか。 | |||||
| ■市長 | 本市として子宮頸がん予防ワクチンの公費助成に向けて取り組んでいく。 | |||||
| (4) | さらに、子宮頸がんは、主に性交渉によって 感染・発症することから、ワクチンの有効性を理解するには、人権教育の一環としての性教育が、必要不可欠だと思う。 そして、偏見や誤解のない知識、態度を身につける必要がある。 まずは、「がん教育」「性教育」推進のため、 関係職員や教職員の研修から早急に始めていかなければならない。見解は。 | |||||
| ■教育長 | 子宮頸がん予防ワクチンの接種については、児童生徒だけでなく、教職員や保護者、市民全体が正しく理解し、偏見や誤解が生じないようにすることが大切である。市長部局との連携を図りながら、教職員を対象とした研修などを検討していく。 | |||||
|
||||||
| 自分の体と性について正しい知識を得る機会とするため、学校での性教育の推進が求められる。 このことが 女性の生涯にわたる「生と生殖に関する健康・権利」(リプロダクティブ・ヘルス・ライツ)を保障することにつながる。 女性だけの問題ではなく、もちろん男性の教育も同時に正しく行なわれるべきである。 この内容を中学校での「生命の尊さ講座」のなかにぜひ含めてほしい。 | ||||||
| ■学校教育部長 | 講座の中に含めて進めてまいりたい。 | |||||
| 2. | 中学生の進路保障について | |||||
| (1) | 2010年度公立高校複数志願入学試験の総括は | |||||
| ■教育長 | 受検者数は前年とくらべ85人の増加。新しい選抜制度導入により、生徒自らの希望、個性や能力等に応じた学校選択が可能になったため、公立高校志望が高まったと受けとめている。 複数志願の状況をみると、第一希望校合格が82%.第二希望合格が15% 目的を持った進路選択がなされたと考えている。 さらに、市内の広い地域から入学者が集まり、今後の各高等学校の活性化が期待できると考えている。 生徒や保護者が、高校の特色について関心をもつようになり、学習に対する関心・意欲が高くなったと報告を受けている。 | |||||
| (2) | 今年度以降の課題 | |||||
| ■教育長 | 生徒自身が一層目的意識を持ち、主体的な進路選択ができるような進路指導体制を充実させていく。 | |||||
|
||||||
| 公立高校不合格者11名から95名と激増した結果について・・ 進路保障はできているのか? | ||||||
| ■学校教 ■育部長 | 適切に私立高校との併願をしており、希望する形で私立のほうの別の進路を実現している。 | |||||
|
||||||
| 進学も就職もできない「無業者」はでていないか? | ||||||
| ■学校教 ■育部長 | 0.76%の子どもたちが、進学も就職もしていない状況が起こっている。 | |||||
|
||||||
| ★最後の教育のセーフティネットとしての定時制高校の必要性を改めて訴える。 ★ (18才までの子ども支援の観点から)不登校や引きこもり等の子どもたちへの支援を卒業後も続けてほしい。 | ||||||
| 3. | 就学前の子どもの 教育と保育の 環境整備について | |||||
| (1) | 本市では、保育所への需要は非常に高く、新しい 保育所誘致も進んでいるにも関わらず、まだ待機児童の解消にはいたらないようである。 保育所待機児童の現状と、今後の解消にむけての 取り組みを伺いたい。 |
|||||
| ■市長 | 平成22年4月1日現在の保育所待機児童は48人となっている。 解消に向けての取り組みは、平成26年度までを計画期間期間とする「たからっ子育みプラン」後期計画において、認可保育所の受け入れ体制の拡充を図るなどにより待機児童ゼロを目指すこととしており、保育所定員を210人増やすことを数値目標として掲げている。 現在、定員90人の新設補保育所整備に着手しており、23年4月開設を目指している。 | |||||
| (2) | 次に、公立幼稚園の活性化の観点から、公立 幼稚園の就園児童数と地域の保護者ニーズの変化をどう捉えているか。 さらに就学前の子どもの教育を市全体で推進していくためにも「3才児保育研究」を新たに進める必要があると考えるがどうか。 | |||||
| ■教育長 | 公立幼稚園の園児数はこの5年間で296人減少している。子どもを取り巻く社会状況や保護者ニーズの変化にともない、就労しながら子育てする家庭や、3歳児から幼児教育を希望する家庭が増えていることが考えられる。 公立幼稚園では、保育所や小学校との連携を図り、研修・研究を深めるなど資質向上に努めている。また、地域のなかで「子育てセンター」的役割を果たすなど、活性化を図っている。 | |||||
| (3) | 幼保一体化への取り組み 子どもの育ち方が保護者の就労の有無や、行政組織の都合によって、幼稚園と保育所に分断されている。 国においては厚生労働省、市では子ども未来部が「保育所」の所管。文部科学省、教育委員会が「幼稚園」という縦割りを維持しているために、就学前の子どもたちが、その年齢に合った必要な教育や保育を受けられない状況が生まれているということではないか。 そのような現状から、国においては、幼稚園と保育所、認定こども園を、すべて「こども園」として一本化する基本方針がまとまっていくような方向性が示されている。 この理念と方向性については、私も望ましいと考えている。ただ、課題解決のための議論がつくされた とはまだ言えないことと、財源保障も十分なされない 中での、早急な流れや安易な結論には、懸念を持たざるをえない。 子どもの育ちの、最低基準が保障される制度なのかを今後も慎重に議論していくことが求められる。 そして、何より大切なことは、「宝塚市としてはどうしていくのか」ということであり、地域の現場の声を提案として届けていくことが必要である。 地域の子どもたちや保護者の抱える問題を把握し、関係機関が連携を取り分担しあえるように、新しい制度への取り組みの第一歩を踏み出していただきたい。 「子どもの最善の利益」のための宝塚市における「就学前の子どもの教育と保育の環境整備について」と、よりよい幼保一体化への取り組みについて伺いたい。 | |||||
| ■教育長 | 本市の就学前の子どもに対する、幼保一体化を含めた総合的施策のあり方については、市長部局との連携の中で、早期に検討していきたい。 | |||||
| 4. | 消費者教育について | |||||
私たちの生活は、さまざまな商品やサービスの情報などがあふれかえっている。しかし、豊かになったその一方では、地球規模の環境破壊も起こり、ごみ処理問題、エネルギー問題、リサイクル問題なども、深刻化している。 私の身近な人からも消費者被害の相談が寄せられた。 |
||||||
| (1) | 消費者の権利を守る取り組みや消費生活相談の現状と消費者教育の推進について | |||||
| ■市長 | 本市の消費者相談の件数は年々減少傾向にあるが、相談内容が複雑かつ多岐にわたっており、一人の相談者に対する時間が長くなってきている。消費生活センターの機能強化を図るため、窓口対応機器等を整備し、相談体制の充実に努めている。 消費者教育の充実については、高齢者や若者などの消費者被害や金融被害を未然に防止するため、小・中学校のPTAや高齢者を対象とした出前講座を実施しており、夏休みには、地域児童育成会を対象とした出前講座を実施する予定。 | |||||
| (2) | 学校における消費者教育の推進について | |||||
| ■教育長 | 豊かで安心した生活を送るために、消費者教育は 必要であり、学校教育の中でも取り組むべきことと認識している。文部科学省からも通知が出され、各学校にも通知した。今後も消費者教育の推進に努めていく。 | |||||